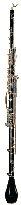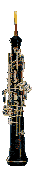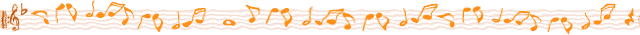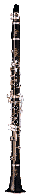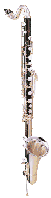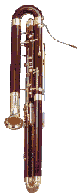木管楽器 2
オーボエoboe,Hoboe,hautbois,oboe
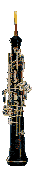
オーボエは、オーケストラの中でも代表的なソロ楽器です。2枚リードで音を鳴らすという、音を出すだけでも非常に難しい楽器ですが、独特の音色をしていて管弦楽曲には欠かすことができない楽器です。オーボエ族の楽器には他に「オーボエ・ダモーレ」や「コール・アングレ(イングリッシュホルン)」などがありますが、フルートやクラリネットよりかなり歴史がある楽器です。
フルートと全く正反対に、オーボエはオーケストラの中に埋もれにくい。逆にいえば、他の楽器との相性をとても気にしなければならない楽器です。他の楽器のアンサンブルに乗っかってソロを演奏する場合はメロディが際立ってよいのですが、伴奏にまわるとメロディを担当する楽器との相性によっては、伴奏が目立ってしまう事すらあります。
Midiの各音源では、中音域は良く再現されていると思いますが、高音域に近付くと実際の楽器よりやわらかく響くようです。実際、オーボエの高音はかなり固めの音が出ます。低音域は、あまり魅力のある音にはならないし、聴き取りにくくなるので要注意です。
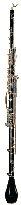
コールアングレ(イングリッシュホルン)english horn,Englisch Horn,cor anglais,corno ingleseは、ちょっと鼻詰まりをおこしたような独特の音で、アンサンブルにはあまり適しません。「新世界より」の第2楽章のような独奏に使われることが多いようです。オーボエより低音域に魅力を持つ楽器で、移調楽器です。F調の楽器が一般的なようです。
ちなみに、フルートの音が出せない私ですが、オーボエは音が出せます。但し、チャルメラの域は脱していません。
クラリネットclarinet,Klarinette,clarinette,clarinetto
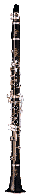
クラリネットは木管楽器の中でも比較的新しい楽器です。バロック時代には使われていません。クラリネットは、サキソフォンと同様1枚リードの楽器です。音を出すということだけに関しては、オーボエなどより簡単のため、初心者が取っ付きやすいらしくブラバンでクラリネットを吹いていたという人がうじゃうじゃいます。
オーケストラの中にはいると、クラリネットの音は非常に溶け込みやすい音色で、特に弦楽器との相性は管楽器の中では抜群に良いのです。但し、高音域はかなりヒステリックな独特の音で響くため、独奏や特に目立たせたいメロディ以外で使用すると、浮き出してしまうので要注意です。
ひとつ厄介なのは、この楽器が主な木管楽器の中で唯一の移調楽器だという事です。通常使われるのはB♭管とA管ですが、たまに1オクターブ高音に移調されるC管なども使われます。また、ピッコロクラリネットにあたるエスクラリネット(Es管)という小さい楽器もあります。オケの中に非常に溶け込みやすいと書きましたが、ソロを吹かせると、ちょっと哀愁を帯びたもの悲しい旋律などは、この楽器の独壇場です。表舞台に登場するのはモーツァルト以降で、モーツァルトもこの楽器の協奏曲を書いています。
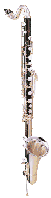
さらに低音を奏するバスクラリネットbass clarinet,bassklarinette,clarinette basse,clarinetto bassoという楽器もあります。形はサキソフォンのように管の下の部分が上向きに折れ曲がっています。使用されるのは後期ロマン派以降の一部の曲で、一般的にはあまり使用されません。キーの間隔も広く体の或る程度大きい人でなければまともに吹けないようです。また、楽器の特性上最弱音で早い動きをさせると、キーを押すカチャカチャ音しか聴こえなかったりします。GSではbs clarinetというパッチがありますが、ちょっと嘘っぽい音です。
バスーン(ファゴット)bassoon,Fagotto,basson,fagotto

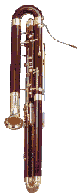
英語では「バスーン」と言いますが、ドイツ語やイタリア語が主流のクラシック音楽界では、通常「ファゴット」と言っています。楽器の名称はこういうパターンが多いですね。イングリッシュホルン=コールアングレ、ダブルベース=コントラバス、ハープシコード=チェンバロ等等。あ、かなり道を逸れてしまいました。話しを戻しましょう。
ファゴットは、オーボエと同じく2枚リードの楽器で、木管楽器の最低音部分を担当します。弦でいえば、チェロにあたる感じですが、それより低い音域が出せるため、コントラバスの役割も担っています。中音域や低音域は、アンサンブルの中で中高音をしっかり支えていますが、高音域は独特の雰囲気をもった響きがするため、しばしばメロディにも使用されます。リムスキーコルサコフの「シェラザード」の第4曲のソロや、ストラヴィンスキーの「春の祭典」の冒頭などを聴いてもらえばその雰囲気がわかると思います。
ファゴットは、非常に細長い楽器でキーを押さえるためにはある程度の手の大きさが必要です。従って、体の大きさも或る程度必要になるため、男性の比率が最も高い楽器のひとつです。昨今、女性の体が大きくなってきて女性ファゴット奏者も増えてきつつあるようです。中学生など体がまだ小さい奏者は、キーに補助器具をつけて押さえられるようにしている方もいるようです。
また、ファゴットは音を出すこと自体は簡単なようですが、指使いが複雑怪奇(運動能力の低い親指もかなり使う)です。あまり大きい音量が出せないため他の楽器の中に埋もれてしまう傾向があるようです。運搬は、4つの部分に分解して運びます。
ファゴットよりさらに低音を出せるコントラファゴットcontrabassoon,Kontrafagotto,contrebasson,contrafagottoという楽器もあります。1800年代後半に改良された楽器が登場してオーケストラ曲で、使われるようになったのですが、この楽器の重低音は、いい加減な練習場などでは床や天井が鳴ります。だいたい、コントラバスとユニゾンで使用されることが多いようですが、楽器の特性上、メロディにはあまり向いていません。発音自体に機動性が無いため速いフレーズを吹かせることは難しいようです。楽器の大きさは生半可なものではないのですが、ファゴットが首に紐をかけて支えているのに対し、コントラは床に置いて支えられるのでファゴットの方が演奏中は肩こりが激しいようです。midiではファゴットのパッチで代用しますが、あの重々しい音色は再現できません。